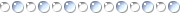|
堕ちる堕ちる
もうどこからが上でどこが下なのかもわからない そんな奈落の底まで二人で堕ちよう
6. escape 朝がきた。世間に背を向ける生活をするようになって数週間が過ぎた朝。 「おはよう」 「ん、……はよ…」 寝惚け眼の新一はそれだけ言うとまた目を閉じて枕に頭を埋めた。快斗はその様子に微笑って瞼に一つキスを落として起き上がる。 「ふぁ〜、朝ごはんなににしよ?」 一つ欠伸をして、テレビのスイッチをつけてキッチンに立った。快斗の怪我は数日で完治して今では何の支障もなく暮らしていた。流行のL型対面キッチンでリンゴの皮を剥きながら、快斗は奥で寝る新一の様子とテレビの画面を見る。ニュースは淡々と昨日起こった残酷な事件、財政の動き、芸能人のスキャンダル、政治、と取留めもなく続く。あれから何日たってもキッドと工藤新一が警察に追われているという情報が流れることはない。元々メディアへの露出を避けていた二人であった為、暫く姿を見せないからといって世間が騒ぐこともない。だがその実一部ではとても騒然としているのも事実。それがいつまでも明るみにならないのは。 箝口令が敷かれてんだろうな…… 快斗はリンゴを剥き終わったところで一つ嘆息した。二人の馴染みの警部たちは気が気ではないだろう。ずっと信頼していた高校生が二人で消えたのだから。公にされない逮捕命令を言い渡されて途方に暮れている姿が眼に浮かぶ。 警察が水面下で自分達を追っている、その気配は肌で感じていた。快斗の変装が見破られることはまずないが、念を入れて隠れ家を転々とした生活をしているのが現状だ。だがこの逃走劇が公になることを一番恐れているのはキッドを追っていた組織の人間だろう。奴らは秘密裏に事態を処理したいはずだ。だからといって軽々しく外に出て行けば二人そろってお縄につくのが関の山。ならどうすれば…?自分達はどうするべきなのか。 何度考えたか知れない。快斗の頭の中では同じ事がぐるぐると渦巻いては絡まって飽和状態であった。 いっそのこと、メディアに情報をリークして組織の連中を警察内部から追い出そうかとも思った。だが、そうすると新一がキッドと裏で手を組んでいたとも取られかねない。新一の名誉の為に、どうしてもそれは出来なかったのだ。 なんて、それはオレの勝手な綺麗事に過ぎないか。 「新一?リンゴあるけど食べる?」 肩を揺すって覚醒を促すと、新一がシーツの中で身動ぎをした。うっすらと開いた目の前に笑顔とリンゴを差し出すと、寝惚けたままの新一がそのリンゴを食む。シャリという音に、罪人である自らの存在を感じる他なかった。 「うまい…」 「よかったv まだあるからそれ食べて目を覚ますんだよ?」 「ん…」 目を半分開けてゆっくりとリンゴを頬張る新一を見て、快斗は言い知れぬ罪悪感を感じていた。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 「快斗、あの宝石どうしたんだ?」 「あ、パンドラのこと?」 「ああ」 目を覚まし、顔を洗ってすっきりした様子の新一は先程とは打って変わって凛としている。パッチリと開いた双眸は青々と穢れのない光を宿す。少し遅めの朝食をとっている新一の口から出たのはこうなった元凶とも言える宝石のこと。 「まだ持ってるよ。あの後暫くしたら赤い光も消えてさ、今はただの高いルビー」 「…どうするんだ?それ。やっぱり壊すのか?」 「そうだな…持っててもしょうがないし、もし組織の手に渡ったら面倒だしね」 「そか。それと、一応聞いておきたいんだけどさ……」 「なに?」 「あれ、本当に不老不死になるわけ?」 「ははっ、なんないよ」 「やっぱりな」 「さすが新ちゃん、現実主義者だねぇ。あれはただの満月で光る不思議石」 「リアリストだ」 「どっちも一緒じゃん。ま、不老不死にはなんないけど、死ぬまで楽して暮らせるくらいの金は手に入るだろうね」 新一は最初から有り得ない事だと踏んでいたが、組織の連中はそんな眉唾ものの話を信じた。 馬鹿馬鹿しいと思うと同時に口惜しい。視線を落とした快斗は脳裏に父の幻影を見た。優しかった父の最期に思いを馳せて、掌に爪が食い込む痛みを他人事の様に感じていた。 不意に表情に陰が差した快斗に新一は手を伸ばして癖のある髪をそっと撫でる。 「なに?慰めてくれてんの?」 「お前昔からそんなだったんだろうなと思ってさ」 「オレ餓鬼じゃねーもん…」 「嘘つけ。今餓鬼になってただろ」 快斗は不貞腐れて新一に目をやって、その目を見開いた。新一にこれ程慈悲深い眼をされたのは初めてであった。そんな眼を見た快斗は、新一の手を取って俯き、雪崩れる様に新一の膝に頭を預けた。そして黙って髪を梳く新一の指を感じながら、眼を閉じた。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 変装と明晰な頭脳をもってすれば余裕と思われた逃亡生活にも、一つ大きな問題があった。 「新一、それあとどれくらいもつ?」 「一週間…だな」 新一の必需品。それは悲しいことに灰原女史の作った薬だ。当然家に近寄ることのできない新一はずっとストックで持たせてきた。そのストックも、逃亡をはかった日の夜に工藤邸から持ち出したものであった。つまり、新しい薬を得るには小さな科学者の力を借りねばならないのだ。 「それ分析して俺が薬作るとか…」 「どうやって?専用機材もないんだ。あったとしても一朝一夕で出来ることじゃないぞ?」 「う〜ん、あのお嬢さんはこの分野のスペシャリストだもんねぇ…」 「そんな灰原が試行錯誤して作ったのがコレだ」 「………………」 「快斗?」 新一が黙り込んだ快斗を覗き込むと、悪戯な眼が光り、次の瞬間にはちゅっと音を立てて短いキスをされていた。 「ば…っ!…お前は〜……!」 「会いに行こうか」 「…え?」 「麗しの科学者さんに」 「博士の家にも奴らが張ってるかも…」 「だったら呼び出そう」 「…あいつ怖いんだからな。こうなった事絶対怒ってるし」 「一緒に怒られればいいじゃん」 新一は一度視線を落とし、再び深い藍の瞳を見上げた。 「…ごめんな」 「なんで?」 「こんな身体でさ」 「それはお互い様だろ?大体オレがキッドじゃなければこんなめに遭わなかったんだ」 「そんな風に言うなよ…快斗がキッドをしてなければ、俺たち会うこともなかっただろうし」 「だったら新一もさっきみたいな事はもう言っちゃダメ!わかった?」 快斗が柔らかく笑うと新一は頬を染めた。 新一は最初に会った時と比べ随分感情が表情に出るようになった。間近でそんな顔を見せられると抱き締めたくなる。自然の摂理に逆らって新一に自分の熱を押し付けてしまいそうだ。そんな危険な綱渡りは出来ないけれど。 快斗は最初相当俺を嫌っていたらしい。それを聞いた時は自分もそうだったとはいえショックだった。だけど、今は優し過ぎて困る。時々、強い欲望を孕んだ眼が俺を捕えるのに、決して抱こうとはしない。それは少し寂しい。 互いしかいない空間で時間が経過するにつれ、二人の世界は着実に狭くなってゆく。 本人達すら気付かぬうちに。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 新一から哀に連絡を入れて、二日もしないうちに哀から連絡が入った。 どうやらこうなる事を予想して、予め薬の用意をしてあったらしい。 「場所は?」 「杯戸シティホテル屋上」 「運命的だね」 「アホか。俺は寧ろ何か起こりそうで…」 「その時はキッド様がなんとかしてくれるよv」 呆れ顔の新一。見慣れたその表情も、少し疲れが見える。気を張り詰めた生活は彼を精神的にも追い詰めているのかもしれない。 「受け取りには二人で行く。それでいいよな?新一」 「ああ」 動き易いようにと待ち合わせの時間は深夜。何度も探偵と怪盗が対峙したその場所で、足音の聞こえる場所へ鋭い視線を送る人が一人。 「こんな時間にレディを外で待たせるなんて、怪盗紳士らしからぬ所業ね」 「申し訳ありません。なにしろこちらは追われる身でして…」 「まぁいいわ。これ、約束の品よ」 普段着で怪盗の雰囲気を醸し出す快斗を一瞥し、隣で黙っている新一へ大きな袋を手渡した。罰が悪そうな顔で受け取る新一の口が開く。 「サンキュ…いろいろ迷惑かけて悪いな」 「なら早く事態を収拾して頂戴。貴方たちの周りの人皆が心配しているわ」 「わかってる…だけど、今は警察が信用できない状態だから」 「信用できる人もいるでしょう?例えば…黒羽君、あなたの隣人の刑事さん」 「駄目だ…オレはあの人をずっと騙してきたんだ。それに、警察は……っ!」 途中、快斗は素早くビルの階段の方へ振り返った。何かと新一もつられてそちらを見る。そこにいた人物に眼をむいた。 「快斗くんっ!!」 「どうして……あなたが?中森警部…」 突如ビルの上に現れた人物に、新一と快斗は驚愕を、哀は変わらず落ち着いた表情を見せた。 「まさか、…お前が?灰原…」 「新一、行こう!」 呆然と哀を見遣る新一の肩を抱いて、快斗が出口へと向かう。それを引き止めようと中森の怒号が響こうかという時、ビルの下でけたたましいサイレン音が鳴った。程なく現れたふらふらと浮かぶ機体は幾度と無く見た警視庁のヘリだった。途端にライトを浴びせられ、真白に染まる視界。快斗は新一を庇う様に背を向け、自らの腕で目の前に影を作った。 「嘘………」 呟いて哀はきっと中森に視線を移す。だが、哀の予想に反して彼も何が何だか分からない、という素振り。哀が軽いパニックに陥っている最中、低く、感情を押し殺した声が哀と中森の心臓を鷲づかみにした。 「お前ら…オレたちを嵌めたのか?」 「ちが……っ…!」 「俺たちを騙したんだな…」 「待ってくれ、快斗くん!」 「おじさん、悪いけどこんな処で捕まる訳にはいかねーんだよ…」 言いながら新一の肩を抱いた快斗は数歩後ずさる。雰囲気がキッドの時のそれになっていることに中森は萎縮した。その瞳はキッドの時にも見せなかった敵意で満ちている。 「待って、話を聞いて!工藤君!」 「聞いてる暇ねーよ…ごめん、灰原」 新一も快斗に任せるだけでなく、大きな袋を抱えたままここから逃げる算段をとっている。終に哀の信用すら危うくなった状況で敵に囲まれた二人は、平素のような冷静な判断力を欠いていたのかも知れない。 結局、その場は、失った信頼を取り戻せぬまま逃げ果せたのであった。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 「薬ちゃんと持ってきた?」 「ああ…」 「これからどうしようか…?」 「わかんねぇ…」 立てた膝に顔をつける。常に無く弱々しい声に快斗が新一の側に寄る。 「どうかした?新一」 緩慢な動作でたおやかな髪を梳いた。 「さっき、父さんのデータベース借りようとしたら…使えなくなってた。もう灰原も何考えてるかわかんねーし…なんか…」 「二人ぼっちだね」 「え?」 「オレもさ、親父の時から世話してくれてる寺井ちゃんって人がいたんだけど…もうずっと連絡とれないんだ」 「俺たち世捨て人になりそうだな…」 「そしたらずっと一緒だね」 「邪魔者いなくて嬉しいか?」 寂しげに揺れていた瞳を悪戯な笑みに変えて、新一は快斗を見上げた。 「嬉しいね。正直、オレ新一さえいれば他はどうでもいいよ。おじさんに嫌われようが世間に憎まれようが、新一がオレの事好きって言ってくれれば幸せだな」 「刹那的だな」 「いいじゃん?それで。…で、言ってくれないの?」 「俺の言葉は安くねーんだよ」 「意地悪…」 気持ちは充分わかってるけどね、と付け足して快斗は膝を抱えた新一を腕に抱いた。 ねぇ、新一 …―――――――――オレ達の世界には二人いれば充分だよね? to be continue..... 何かと間違っている二人。 |