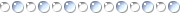|
お前の言葉は夢のような響き
その挙止は甘美な誘い 全て、誰にも渡さない いつか、二人闇に呑み込まれようとも だけど僕らは手を合わせて請うのだ 願わくば願わくばそれがもう少し先のことでありますようにと――――――
4. infinity 「お前、怪盗失格だな」 「はぁ!?何だよ、いきなり!」 「ここは俺んちだ。そこでてめーは寛ぎすぎだ」 新一は毎夜やってくる怪盗にぼそぼそと呟いて嘆息した。 怪盗と言っても今はTシャツにジーンズ姿の至って普通の若者である。それがソファに寝転がって雑誌を捲っている姿は我が家にいるようにしか見えない。 「だってココにいると落ち着くしー家より広いしー」 「はぁ・・・・・・・・・」 足を組んで快斗の向かいのソファに座り推理小説を読んでいた新一はまた一つ溜息を吐いた。 「そんなに悩ましい声ばっかり出してたら幸せが逃げるぜ」 「何が悩ましいだ。それに元はと言えばお前のせいだ」 じろりと睨んで新一が小説に眼を戻そうとするとその本が一瞬で忽然と姿を消した。 仕掛けたであろう張本人を再度睨むと思いの外真面目な表情をしていた。 「なら、少し真面目な話をしようか。新一」 沈黙・・・・・・ 「何か反応してくれないと困るんだけど・・・」 「嫌な予感がするから辞めとく」 「先延ばしにしても、いつかは絶対に聞くよ」 それを聞いた新一は迷ったような、戸惑いの表情を見せた。それを視界に入れながらも快斗は口を開く。 「あの日・・・オレを助けてくれた日、どうしてまたキッドの現場に来る気になった?」 雑誌をテーブルに置き、ソファに座って新一と向き合った快斗はいつになく真面目な表情でまっすぐに視線を寄こした。 「聞きたいのか、そんなこと」 あまり言いたくない、と新一の顔に書いてあったが快斗は引かなかった。 「聞きたいね。あれ程キッドを拒んだのに、怪我を治療してくれたと思ったら、現場に顔出すとまで言うし。危害を加えた覚えしかないこっちにとっては不思議でしょうがないんだ」 「危害っつってもなぁ・・・あの時はお前に首やられてなくても薬なんて飲める状況じゃなかったぜ?俺は寧ろお前が居て助かったと思ってんだけど」 「じゃあ何であんなに怒ってたんだよ・・・」 今のはオレを労ってくれたのか?それとも本気でそう思ってる? あの首の痣を見れば苦しみを助長したことは明白なのに・・・ 「それはお前が自分のせいだ、悪い事したーって顔してたからだな」 「オレのポーカーフェイスはどこへ・・・それで、何で現場復帰してくれたのかな?」 新一のプライドの高さは短い付き合いながらもわかっていた。今ならあの時謝るべきではなかったこともわかる。それは新一の神経を逆撫でする行為だから。なのでその件については深く追求しないことにする。 微妙に話を逸らされている事に気付き、快斗は笑顔で新一に本題を突き出す。 「またそれかよ・・・大した理由なんてないぜ。多分、お前が怪我したから・・・だな」 「はぁ・・・怪我・・・」 「怪我したお前を家まで引き摺って運んで治療して、警視庁で宝石を借りてきて見せてやったら俺に借りができるだろ?だったら交換条件になんかさせてやろうと思って、考えたんだ」 「それと現場復帰と何の関係が・・・」 「まぁ、聞け。それで思い浮かんだのがまたお前の作った暗号を解きたいってことだったんだ。純粋に楽しんで参加できるのってキッドの現場だけだからな・・・あんな風に啖呵切っといてなんだけど、結構後悔してたんだろうな」 「なんか微妙に照れる・・・」 「だから言いたくなかったんだ・・・」 「でも、後悔ならオレのほうが大きかったと思うよ。新一がそう言ってなくてもキッドからラブレター出してたよ。ビルの屋上に降りる時はいつも新一の姿探してたし。でも結局いつも見つからなくて、オレのこと恨んでるんだろうなぁって屋上で黄昏たりして」 「それで撃たれてりゃ世話ねーよ」 べろと舌を出して揶揄すると快斗がひどぉーいとおどけて見せた。新一の照れ隠しだとわかって敢えて快斗もけらけらと笑って流す。 なんだかお互いに気恥ずかしい事を言い合ったような気がして、それきりその話題が出ることはなかった。 言うなれば以前の自分達は互いに銃を突きつけている状態で、相手の様子を窺ってばかりだった。だから、非生産的に罵り合い、弱みに付け込んで少しでも優位に立とうと必死だった。しかし、銃を下ろして向き合ってみると、まるで噛み合わなかったピースがぴったり嵌る様に二人でいるとしっくりくるのだ。快斗は新一の意外に子供っぽい性格と柔和な表情に、新一は快斗の明朗活発さ、豊かな感情表現に新鮮味を感じて現場とのギャップを垣間見るたびに笑みを溢した。そして、隣家の科学者の言う「ハリネズミさんはウサギにでもなったのかしらね?」には共に頭に疑問符を浮かべるのだった。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 二人が毎日平和に過ごしているわけはなく。 寧ろ、二人共に穏やかに過ごす日の方が少なかったりする。 「なぁ、そろそろ帰ったら?」 「えー、何で?泊めてよー」 ピコピコとゲームをしていた手を休め、後ろの新一の言葉に振り返って返事をする。キッドの仕事を終え、羽休めにと寄った工藤邸に思いの外長居をしてしまい、面倒だからこのまま泊まっちゃえと思っていた矢先の言葉に違和感を感じた。こんな事はよくある事で、いつもなら新一もこの時間まで居れば泊まるのだろうと暗黙の了解でいてくれたのだ。 「あのなぁ、ここはお前の宿かよ・・・」 「第二の故郷だよv」 言い返す気力もないのか、新一はソファに突っ伏してしまった。 「新一」 「ナンだよ?」 「強いのと、無理するのとは違うからね?」 顔にかかる前髪を梳いて、咎める様な視線を向けて告げる。いつものことながら、本当に側にいる方の身にもなって欲しい。こんなに顔色の悪い人間を置いて早く帰れなどどの口が言うのか。って新一の口か。 「哀ちゃん呼んでくるから、此処で大人しくしてるんだよ」 「餓鬼扱いすんじゃねーよ」 頭を撫でて言えば新一の口から不平が漏れる。だがそれを口にすることすら億劫な様子に快斗は言いようの無い不安に駆られる。新一の体調が崩れる度にフラッシュバックするのだ。あの日の我を忘れて苦しむ新一の姿が。 心臓に悪いよ・・・オレが早めに帰ってたら、今日新一の体調が悪かったことなんて一生知らないままなんだろう。 それが新一の望むところだとしても、納得がいかないのだ。せっかく縮まった二人の距離をまた広げるような気がして。 「哀ちゃん、新一が具合悪そうなんだけど」 『わかったわ、すぐ行くわ』 隣家へ直接呼びに行こうかとも思ったが、少しでも新一の様子を見ていたくて、電話で簡単に様子を伝えた。短い応答の後、科学者のあの子は診察道具を抱えて工藤邸に現れるのだ。 「新一、もうすぐ哀ちゃん来るって」 「ああ、サンキュ・・・」 「どこか痛い?」 「ん・・・喉・・・とか」 新一の言葉に一瞬身体が強張った。眼を閉じている新一は気付かなかったが、快斗の顔は誰が見ても分かるほど青褪めていた。 そっと手を伸ばす。今はもう消えたあの痣が脳裏に蘇り、憑かれたように細い首に手を這わせ指の腹で優しく撫でた。 「何すんだよ・・・」 慣れない感触を感じた新一はうっすらと眼を開けて自分の首を凝視する快斗を見る。すると快斗は酷く辛そうに端正な顔を歪めて新一の身体に覆いかぶさった。 「新一・・・」 「どうしたんだよ、快斗」 新一の首筋に顔を埋めた快斗は暫く無言で新一の頭を抱きかかえる。新一に自分の体重がかかり過ぎないように注意を払っていたのは恐らく無意識だろう。 「オレ、今は新一が可哀想って顔してないだろう?」 「ああ、・・・」 確かに前のようなあからさまな同情はしていない。だけど、今のお前は・・・ 戸惑いを隠しきれないまま言うと快斗が新一の顔の隣に手をついて上体を支えて顔を上げた。 「でもね、何でかな・・・前よりずっと辛いんだよ・・・・・・」 「快・・・、斗」 哀に染まった紫紺の双眸が綺麗だと思った。夜を駆けるキッドを思わせるその色に魅入られて身体の痛みなど彼方へ飛んでしまう。だから、手を伸ばす。 自然に、どちらともなく眼を閉じて、ゆっくりと顔が近づいた。 後の事など考えもしない刹那的な行動を遮ったのは玄関の物音であった。閉じかけた眼を開くと間近で視線が絡む。 「灰原だ・・・」 「そうだね」 至近距離に見る相手から少し顔を逸らし、快斗は上体を起こしながら新一の髪を梳いてやった。 「続きは、また今度な」 快斗がはっきりと新一に告げると同時にリビングの扉が開く。 「あら、お邪魔しちゃったかしら?」 顔を離したとはいえ、快斗はソファに寝ている新一の顔を覗きこんで頭を撫でているところだ。傍から見れば明らかに甘いムードなのだ。 「ちょっとね〜、じゃ後は哀ちゃんにお任せするよ。オレは何か消化のいいもの作ってるから」 新一の上から退くと快斗はひらひらと手を振りキッチンへ直行する。 後に残された頬を染める探偵に向かって哀は溜息と共に呟いた。 「いい旦那持ったじゃない、工藤くん」 「だだ誰が旦那だっ、せめて奥さんにしろ!」 「思ったよりも元気そうでよかったわ・・・でも顔色は良くないわ。あの人がいたから良かったけど、次からはもっと早く連絡して頂戴」 「わかってるよ・・・」 「貴方のその言葉を聞くのは何度目かしら?もっと自愛なさいな」 それが貴方には足りないのよ。でもあの怪盗さんは思った以上に工藤くんに好い影響を与えてるのね。禍転じて福となすってところかしら。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ そんな事があってから、二人の関係は微妙に変化した。 「じろじろ見るな・・・」 「いつもながら凄い量だと思ってさ」 じゃらじゃら音を立てて新一の口に放り込まれていく錠剤。 「いい加減見慣れただろ?」 「見慣れないよ、ていうか前より量増えてない?」 常人には見ただけでは分からない(それ程元々大量であった)が勘のいい快斗には分かってしまった。 「無駄に働く頭だな」 ちっと舌打ち交じりに告げる新一に複雑な表情を向けて 「無茶して現場でぶっ倒れんなよ。オレが哀ちゃんに叱られる・・・」 「わかってるよ」 「ならいいけどさ。じゃ、オレ先に行ってるわ。後でな、新一」 俯いてしまった新一の頬に掠めるように素早くキスをしてにっこりと笑った。新一はばっと快斗が触れた頬に手を当てて目の前で何事も無かったかの様にしている男を睨む。 「いいじゃん、減るもんじゃなし」 「減るとかじゃなくて、いきなりすんなよ!びっくりするだろーが!」 「へぇ、いきなりじゃなかったら何してもいいわけ?」 「そんなわけあるかっ!もういいから、さっさと行っちまえ!」 かーっと頭に血を昇らせて飄々としている奴に言うと、したり顔で手を振り工藤邸を去って行った。 あー、有り得ねぇ。何で男の俺にキスするんだ?頬だけど・・・普通しないだろ?!あいつは軽いから誰にでも出来るのだろうけど、される度に鼓動が早くなる方の身になれってんだ! 友人と呼ぶにはあまりにスキンシップ過剰な俺たち。だけど、こ・・・恋人と言えるほどの仲ではない。宙ぶらりんなこんな関係につける呼称はないものか、と新一はコーヒーを啜りながら思う。 「ライバル、悪友、仲間、親友、ステディ、運命共同体、恋人・・・」 どれも当て嵌まりそうでいてまるで違う。今更だが特殊だ、自分達の関係は。 目についた新聞の一面を広げてたった今出て行った人物を思う。白い装束に不敵に笑みを象る口元。その存在が人々を魅了して止まない白き罪人。 「今日こそパンドラ・・・だといいな。快斗」 ふっと笑って自分も支度をするべく、二階に上がった。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 「いたぞぉー!キッドだっ!!」 「今日も精が出ますね。中森警部?」 目当ての宝石を手中にしたキッドは威嚇用にトランプ銃を向け、口角を上げて中森を挑発する。 「今日こそ捕まえてやるわー、キッドォオー!!」 おーおー、すげー気合入ってんなぁ、中森警部殿は。だけどそれも空回りだよ。 例の如くダミーを追いかける警察の姿を確認して警官に化けようとマントの端を掴んだ時、突き刺さるような視線を感じた。 突如背後に並々ならぬ殺気が立ち込め、全身が総毛立つ。ねっとりとした嫌な感じが辺り一面を包むのがわかった。冷や汗を流しながら相手の動きに神経を集中させる。 気配を絶っていたのか・・・気付けなかった。相当腕の立つ奴か? 「怪盗キッドだな?個人的な恨みはないがここで撃たせてもらう」 それだけ告げると相手は姿も見せずに暗闇から銃を放つ。ここは美術館の中。まだ出口付近には警官が張っている。ぎりぎりで銃弾を避けるも、容赦のない発砲は確実に身体を掠めつつある。 こりゃ、新一のいるビルまで行けそうにないな・・・ 呑気にそんなことを考えていると肩に激痛が走った。思わず体勢を崩し蹲ると暗かった館内に突如光が射す。眩しさに眉を顰めて見たその先には予想だにしなかった人物。 「ど・・・して・・・・・・ここに?」 敵は彼が来たことに気付くや早々と姿を消した。ドクドクと脈打つ肩を押さえながら、罰の悪さに眼を逸らして彼に問う。 「・・・第六感ってやつだよ」 「助かりましたが、今名探偵の手を借りるわけにはいきません」 「怨み言なら後でいくらでも聞く。だから、大人しく俺について来い」 膝をつき蹲るキッドの目の前に立ち、新一は手を差し出した。 「・・・・・・二度目ですよ、この光景は」 出来れば二度とこの手を煩わせたくはなかったが・・・ 「あの時はお前の意識はなかっただろう?」 優しい笑顔。あの時と同じだ。手の冷たさも、凭れて香る彼の匂いも何もかも。変わったのはきっと、オレたちの距離だけ。 「少しは覚えてますよ」 新一は肩の血の量に秀麗な眉を顰め、キッドに肩を貸し美術館の従業員出口から外へ出た。出口に警官がいなかったのは新一の指示のおかげなのだろう。そのままキッドは待機していた博士のビートルに乗せられ、その小さな車は工藤邸へと疾走した。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 工藤邸に着くなり哀に血の滲むシャツを剥ぎ取られ、止血を済ませた後患部の治療をしてもらった。前までは怪我をした時は自分で手当てをしていたが、こうして信頼できる人に診て貰えるのは幸せだ、と感慨に浸ってしまう。 「血は出てるけど傷は浅いわ。貴方なら数週間もすれば元に戻るでしょ」 「ありがとう、哀ちゃん。新一は?」 「貴方をここに置いた後美術館に戻ったわよ」 カチャカチャと鞄に医療道具を詰め込んで哀は事も無げに告げる。 「はぁー、また借り作っちゃったな・・・」 情けねー・・・天下の怪盗キッド様とあろうものが 「貴方、前に言っていたわよね?覚えているかしら?工藤君と離れるって言ったこと」 「あなたたちは一緒にいては駄目ね。近づくほどにお互いを傷つける」 「だったら離れればいいだけだよ」 「言った、ね・・・」 ぽりぽりと頭を掻きながら決まりが悪そうにする。 「どう?離れられなくなった気分は」 「随分不躾ですね・・・」 「見ていればわかるわよ。彼が可愛くて仕方がないんでしょう?」 「まぁね・・・」 「早くしないと横から誰かに奪われてしまうわよ?敵は多いんだから」 そう言って妖艶な微笑を浮かべる哀を見て快斗は一瞬呆ける。 「哀ちゃんさぁ、元の身体に戻らなかったのって・・・」 「わかっても工藤君には言わないで。気を遣わせたくないのよ」 「じゃあオレがあいつ口説いてもいいの?」 「結構よ、好きにして頂戴。私としてはお守りが多いほうが助かるわ」 「お守り・・・・・・ってぴったりな言葉か」 なんて言われようだ・・・と思ったが彼の無鉄砲さを考えると成程それも納得がいく。 「そろそろ彼が帰ってくるわよ。精々機嫌を損ねないように注意することね・・・」 哀の言葉に快斗は首を傾げる。新一が怒ることなんて今の状況では考えられなくないか?と疑問に思っていると意味深な笑みを残して阿笠邸へ戻って行ってしまった。 その後快斗は帰宅した新一にヘボだのボケだのバカだのと罵られ、鳩が豆鉄砲を食らったように呆然とし、なんでだ!?と自問自答をする破目になる。それが怪我をしたことを案ずる新一なりの歪んだ愛情表現であることに気付くのには少々時間を要するのであった。 現段階で新一の理解度に関しては哀ちゃんに負けてないか?と一人落ち込む快斗であった。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 哀の冷やかしの視線に耐えながらも二人穏やかな生活が続いていた。そんなある日。 「快斗、今日学校終わったら本屋付き合ってくんねー?」 付き合っているわけではないのだが何故か朝はいつも一緒で。快斗が泊まった日はそのまま工藤邸から、そうでない日も快斗が朝早くから工藤邸へやって来ては寝起きの悪い新一を急かして其々の学校へ行くのが日課となっていた。 隣家の科学者曰く、付き合う事秒読みの中学生カップルのような初々しさで見ていて呆れるしかない、らしい。 「あー・・・ゴメン、今日ちょっと用事あってさ。本屋は付き合えないけどそれ終わったら夜に遊びに行きたいんだけど、いい?」 心底申し訳無さそうに謝る快斗に新一は微笑を返した。断りを入れるだけでなく、すぐにそれをフォローする快斗に本当によく出来た人間だと感心すらしてしまう。 「わかったよ。じゃあ夜にな」 分岐点で帝丹と江古田の生徒が篩いにかけられたように別々の道を行く。同様に二人も軽く手を振って別れた。 バタバタバタッ・・・バタン! 「どうしたのよ?」 この家の主が珍しくそれはそれは大きな足音と共に現れ、哀は眼を剥いて紅茶カップから手を放す。 「勝手に上がってたわよ」 それはいつものことなのだが、反応のない相手に取り敢えずの言葉をかけて様子を窺う。 「・・・え?ああ、灰原か。来てたのか・・・」 「ぼーっとしちゃってどうしたの?本買ってくるんじゃなかったの?」 「え・・・・・・あ、どっかに忘れてきたみてー」 本当にどうしたのかしら?あんなに楽しみにしていた本を忘れるなんて。普段しっかりしている人の今のこの有様は何? 「何かあったのね。黒羽君のことで・・・」 「なっ、何でそこで快斗が出てくるんだっ!」 鎌をかけてみれば明らかな狼狽え振り。隠せてないわよ、工藤君・・・。 「そんなに挙動がおかしくなってしまうくらいなら、いっそ言ってすっきりしたら?」 「別に俺おかしくねーし」 「あのねぇ・・・まったく、どうしたもんかしら・・・」 はぁと溜息を吐いて紅茶に口をつけ、暫く黙っていると観念した新一が口を割った。 「快斗が、・・・・・・・・・・・・楽しそうに女の子と歩いてたんだ」 「あら」 「俺が本屋行きたいって言ったの断ってまでさ、会わなきゃいけない相手だったんだろうな」 「貴方だって蘭さんと出かけたりするじゃない」 「最近はどこにも行ってない」 眉を顰めて不貞腐れたように言う探偵を見て哀は全てを理解した。 「・・・・・・・・・それに腹が立って怒って帰って来たってわけ?」 呆れた。出会ってからの数々の言動の中で一番呆れた。この様子では何故今自分がイライラしているのかもわかっていないのだろう。自分を差し置いて他の人しかも女性と会っていたことに怒りにも似た感情を抱えているのだ。立派な嫉妬ではないか。 「彼だって男の子なんだからガールフレンドの一人や二人や十人はいるわよ」 「十人・・・あいつなら有り得るな・・・」 哀がからかおうとして言った言葉に新一は思いの外納得してしまった。顎に手をかけて考え込んだ後顔を上げると儚い笑顔を浮かべて呟く。 「ま、俺には関係ないことだけどな・・・・・・」 ・・・御免なさい、黒羽君。余計な事言ってしまったみたいだわ。でもいい切欠になるでしょうし自分で収拾つけなさいよ? 「今日も彼来るんでしょう?その時に聞いてみたらどう?彼女いるのか、とでも」 「聞く必要ねーだろ。俺はいつも通りにするだけだ」 意地を張っても今の状態が既に普通じゃないのよ。絶えず寂しそうな眼をしちゃって、今に黒羽君が心配して構い倒してくれるわ。 哀は新一に本来の目的であった薬の事を告げると阿笠邸へと戻った。新一はというと正体のわからぬ感情を持て余しながら小説を読んで時間を潰すのであった。 「今晩はー」 形だけ挨拶をして我が家のようにずかずかと入る。反応がないのはいつものことのなので深く考えずにリビングの扉を開けた。 「新一、居るんだろ?」 あれ、ソファから足が見えるのに返事がない。そうっと近づいてソファの背で隠れていた上半身を見ると新一は腕を枕にして横向きに寝てしまっていた。お腹の上に伏せてある本を読みながらうとうとしていたのだろう。 「無防備の極みだな・・・」 髪を梳いてやると気持ち良さそうに喉を鳴らした。 「妖艶だねぇ・・・新一くんは」 生殺しだ・・・とこっそり心で非難しながら頬に軽くキスをする。 いつもはすると怒られるんだよなぁ。でも本気で嫌がっているんじゃなくて、どっちかというと照れているに近い。ずっと二人の関係を明白にせず、不即不離の状態を続けていたけど、――それが心地よかったから――そろそろ頃合かもしれない。甘酸っぱい関係も新鮮で楽しかったが、いい加減身体がもたない。 「新一、もう七時だよ。いつまで寝てるつもり?」 耳元で甘く囁けば新一は身体を捩って離れようとする。 「起きないと悪戯するよ」 僅かな反応を返す新一の上半身を起こして自分に凭れさせ、背中に不埒な手を滑らせる。シャツを捲り上げながら直に背をなぞるとピクと新一の身体が一瞬強張った。 「ン・・・・・・ぅ・・・っ」 あ、なんかイイ匂い。いつも近くで感じてるそれ。それに身体が温かい。 「か・・・いと・・・・・・?」 「あ、起きた?おはよう新一」 「なんでここにいるんだ?」 「やだなぁ、来るって言ったじゃん」 そういえばそうだった。女の子と会ってから俺のところに来るんだったな。 寝惚けて忘れていた事実を思い出し、眉間にシワを寄せて密着していた快斗の肩を押して離れようとする。 「ああ、・・・思い出したよ」 「新一?」 急に不機嫌を露わにする新一の顔を覗きこむもプイッと顔を背けられてしまう。 「こらこら、何拗ねてんの?」 「拗ねてねー」 「そーいうこと言うんだ」 ニヤと性質の悪い笑みを浮かべて快斗は再び不埒な手を動かした。 「なっ、・・・ちょ・・・っ・・・と!」 「なぁ、どうしたの?言えよ、新一」 「手、やめろよっ!くすぐったいから」 「ちゃんと言わないと離さない」 「・・・・・・・・・っ、・・・お前が、彼女いること言わねーからムカついたんだっ」 「ふ〜ん、新一の中ではオレに彼女がいることになってんだ?」 散々手を滑らせた後、快斗は新一の言葉に不快指数を上げて手を離した。新一はやっと解放されたことに安堵していてそれには気付かない。ささっとシャツを整えて快斗を睨む。 「それ誰かに聞いたわけ?」 眼を薄く開いて新一を見据える快斗。射抜かんばかりのその強い視線に新一は怯む。 「・・・・・・・・・直接見た」 ぼそっとか細く呟くと居た堪れなくなりソファから離れようとしたが、快斗に阻まれる。 「オレの言葉を聞く気はないのか?」 「聞く必要ないから」 「じゃあ勝手に喋るから聞けよ」 「俺に命令するな」 新一が眼光鋭く快斗を睨む。一瞬即発の空気。探偵と怪盗の頃が蘇ったように二人の間に緊迫した空気が流れる。 「は、・・・わかったよ。余計な事は省いて単刀直入に言う。オレが好きなのは工藤新一だけ。だから彼女はいない。彼氏は新一次第でできるかもしれないけどな」 「・・・・・・・・・下手な嘘つくなよ」 「嘘なわけないじゃん、というより今までのオレの態度で少しは気付いてるものだと思ってたよ」 鈍さもここまでくれば感嘆する。さっきは思わず感情的になりかけた快斗だったが落ち着いて考えればこれはステップアップの絶好のチャンスなのだ。この機会を逃す手は無い。 「嘘じゃねーの・・・・・・?じゃああの子は・・・」 徐々に新一の顔に赤みが差してきた。いつもと変わらない口調で告げられた事実に戸惑いを感じながらも心につっかえている少女のことを問いただす。 「あれは幼馴染み。新一で言うところの毛利蘭サン」 言葉に棘があるのは快斗のほうにも新一の幼馴染みに対しての嫉妬があるからだ。それを棚に上げて自分ばかり疑われるのは少々癇に障るというものだ。 「でも、・・・・・・お前が・・・」 すごく楽しそうに見えたから腹が立った、なんて死んでも言えない・・・ 「何?まだなんかあるの?」 「別に。てか何でお前怒ってんだよ?」 「怒ってないよ、新一が全然返事する気ないからって怒ったりしないよ」 「説得力ねーな・・・・・・」 「性質悪いよねぇ。本当はどこかで気付いてて知らない振りしてたんだろ?」 快斗はにこにこと笑いながら新一の腕を掴んで口に甲を宛がう。軽く口唇を触れさせて上目遣いに見た後、腰を引き寄せた。 「お前がどっちつかずな態度取るからだ・・・俺はこういうの慣れてないから混乱しちまう」 全部お前が悪いんだ。人の心を散々掻き乱しておいて、俺を置いて女と会ったりするから。 新一は腰に固定された腕に手を重ね先を促すように快斗を見つめた。 「前の続きしようか?」 低く甘く囁かれた言葉に抗う術はなかった。 「新一・・・・・・口唇柔らかいね」 「誰と比べてっ・・・・・・んぅ・・・っ・・・」 皆まで話す前に柔らかいらしい口唇を塞がれて、器用な手で腰や脇腹を愛撫される。慣れてる・・・と考えてしまうと悔しいが、今は唯この熱に浮遊してしまいそうになる意識を保つ事で精一杯であった。 「しんいち・・・・・・」 「・・・・・・かい・・・と」 キスの合間に漏れる声はどこまでも甘く、官能を刺激した。新一の眼からは生理的な涙が流れ、快斗はそれを追って頬や顎に唇を滑らせる。 「甘いね、すごく」 「ばっ・・・かじゃねーの・・・?」 「本当だよ、食べたいくらい」 かぷっと新一の下唇を甘噛みすると新一が膝を折ってソファに倒れこんでしまった。それに合わせて快斗もソファに乗り上げ新一の上に覆いかぶさっては飽きずに甘い口唇を貪る。 「ン・・・っ・・・・・・も・・・・・・しつこいっ・・・て」 けれど快斗を押し返す力は弱い。息苦しそうな新一を見て一呼吸おこうと新一の髪をかき上げて額を露わにし、そこにちゅっと音を立てて口付ける。 「・・・・・・キス魔」 「酷いな」 「いつまでするつもりだ」 「ん〜、・・・・・・無限に?」 頬の色づく新一に煽られて再び未だ熱を持つお互いのそれを重ねる。深くなるそれに眩暈すら感じながら新一は置いて行かれぬようにと快斗の背に腕を回し服を握り締めた。 漏れる媚声 伝わる熱 交わす想い 肌に残る所有の証 ああ、願わくば願わくばこの時間永遠に続かんことを――――――― to be continue..... この話の快斗は落ち着いた雰囲気にしたかったんですけど、ちょくちょくお調子者の匂いを垣間見せる始末・・・落ち着け! |