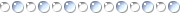|
そんなに俺が可哀想なのか? 力で太刀打ちもできなくて、薬にまみれた非力な俺が憐れだと言うのなら、もうお前の顔など見たくない。 悲しい事にお前のポーカーフェイスは俺には通じないから。
2. resistance 「どうも」 「なっ・・・・・なんで?」 やっほーとでも言いそうな雰囲気でにこやかに現れた白装束の怪盗をすぐに家に引き摺り込んだ。 今日は現場には行ったがすぐに帰って来たのでこの怪盗には会わないはずであった。これでイライラせずに済むと考えていた新一にとっては彼の出現は寝耳に水である。 一方怪盗のほうは、簡単に家に入れた探偵に内心驚きながらも表面上は笑顔で腕組みをして眉間にシワの寄った探偵を見ていた。 「どういう了見だ・・・・・?」 低い声で睨みながら自首でもしにきたか?と嘲笑して怪盗を見る。 「今日は現場にいらっしゃらなかったようなので・・・・・」 「なんだよ、俺に会いたかったなんて言うんじゃねーだろうな?」 「会いたかったですよ?あなたの屈辱に歪む顔を見たかったですね。逃げられてはそれも叶いませんが」 「逃げるだぁ?てめーなんかに使う時間が惜しいから帰ったんだよ。俺はコソ泥に付き合うほど暇じゃないんでな」 最初は穏やかに腹の探りあいをしていたが、会話が進むにつれ次第に双方の化けの皮が剥がれ始める。 「捕まえる自信がないからそんな風におっしゃるのでしょう?」 「ハッ、心配しなくてもテメーは俺が監獄にぶち込んでやるよ・・・・そうすればその減らず口も叩けなくなるさ」 「それはこちらの台詞ですね・・・・・あなたはいい加減目障りなんですよ。暫く現場に来れないようにしてさしあげますよ?」 いつまでも罵り合っていてもストレスが溜まるだけだ。キッドの出す殺気に怖気づく様子のない新一に痺れを切らし、快斗はゆっくりと両手を上げた。 白馬はちょっと脅せばすぐ消えた。でもこいつはそうはいかない。気が進まないけど少々苦しい思いをしてもらうしかないな。 「・・・・・・っう、ぐ!」 快斗の手は新一の首にかかった。力を入れると新一が信じられないという表情でキッドである快斗を見る。もちろん本気で殺す気などさらさらないが、この厄介な探偵を黙らせるには多少の脅しでは駄目なのだ。キッドを恐ろしい存在と認識するように徐々に力を入れる。 「・・・・ッ・・・ハッ・・・」 喋る事もできず、眼を瞑って首の圧迫感に耐える。次第に喉からヒューヒューと喘息のような音がして、新一の額には汗が光った。震える手でキッドの手を外そうともがくが手袋をがりがりと引っ掻くだけで何の意味もなさない。 「死にたくなかったら、もう邪魔はしないで下さいね?」 仕上げとばかりに殺気を込めて言い、失神寸前の新一を解放した。すると足に力が入らず、新一は床に座り込んで手をついて上体を支え、込み上げる嘔吐感に耐える。 突然、全身を切り裂くような激痛が新一を襲った。喉へのダメージで息をするのもままならない、首が麻痺したように感覚がない、そんな時に最悪な事態が起こる。 く・・る・・・・しいっ・・・からだが・・・痛いっ! ドックドックと心臓の音が響く。首の痛みに加え発作の症状が起こり新一は自分の置かれた状況に絶望感を抱いた。 ここは玄関だが薬はリビング、近くには今自分を殺しかけた怪盗。無駄に大きいこの家をここからリビングまで行くのは相当にきつい。だからといって怪盗の世話になどそれこそ死んでもなりたくない。きっとこの怪盗のことだから自分が嘆願でもしない限り助けてなどくれないだろう。 まじで・・・・・死ぬかも・・・ 「いつまで座っているんだ?」 キッドは暗に立てと言って新一の顔を覗き込もうとした。 「帰れ・・・・・」 喉を痛めてかすれた声で言う新一の身体が小刻みに震えていた。恐怖に震えているのならばキッドの目論見どおりだが、新一は左胸を押さえて荒い呼吸を繰り返していて、快斗はただならぬ様子に漸く彼に何かあったのだと悟る。 「くど・・・」 「っ!ゴホ・・ッ、ゴホッ・・・・・・グッ・・・」 名前を呼ぼうとした瞬間、今まで以上に苦しみだした新一にキッドの手が伸ばされた。 パシッ・・・・・・・ 渇いた音が玄関に響き、キッドの手は赤くなって宙に浮いた。 「らしくね・・・っ・・ウッ・・・グ・・こと・・・すんなっ!」 やっとの思いでそう言うと新一は壁づたいによろよろと歩き出した。 「ハッ・・・ハァッ・・・・・ッ・・」 彼の身に何が起こっているのかまったくわからない快斗は時折喉を詰まらせては苦しそうに呼吸をする新一を見て何故だか泣きたい気持ちになった。 なんであんなに苦しそうなんだよ・・・・・?あれは首のせいだけじゃないだろ? 心臓が痛むって一体どういうことなんだよっ・・・・・・・! リビングへと向かう新一の手助けをするでもなくただその場で呆然としていると、新一の首を絞めたときの感触が甦ってくる。 オレはただ、首に痣でも残してあいつがビビればそれでよかったんだ・・・・・殺したかったんじゃないっ! 快斗が葛藤している間に新一は今にも倒れそうな足取りでリビングのドアを開けていた。自分も中に入ろうかと逡巡していると開きっぱなしのドアから何かが落ちた音とザーという床に何か硬いものが散らばる音がした。 いてもたってもいられずに快斗がリビングへと入ると新一はラグの上に座って上体をソファにあずけて震えていた。 快斗は新一のその姿を視界に入れる前に床に眼が釘付けになる。 床に散らばる先ほどの音の正体はおびただしい数の錠剤であった。隣家から持ってきていた紙袋が乱暴に破られて床に落ちているのを見て、さっきは薬を取りに行っていたのだとわかる。 色とりどりの錠剤は何種類もあり、床に散らばるその様子は幼い子供の落書きのようだった。そのカラフルさが事の深刻さを嘲笑うかのように眼についた。 「・・・・・ハッ・・・・・ゲホ・・ッ!」 ソファの背で隠れて見えない新一はさっきよりも苦しそうで、快斗は近寄って様子を見た。 苦しさから掻き毟った腕は血が出てぼろぼろになって、眼からは絶えず涙が落ちていた。彼の手にはいくつもの錠剤が握られていたが彼の症状が良くなる気配がまったくない。むしろ酷くなる一方だ。 ふと見た快斗の眼に新一の首の痣が映り愕然とした。新一は薬を飲んでいないのだ、否、飲めないのだ。快斗が痣になるように強く締めたことで薬が喉を通らず、発作も一向におさまらない。 マジかよ・・・・・・?このままじゃオレがこいつ殺すことになんのか? だって、こいつがこんなだなんて知らなかったんだ。いつも超然としてるから、弱いところなんてないと思ってた・・・・・だから、余計に憎かった・・・ 「いたい・・・・いた・・・いっ・・・くるし・・・っ」 か細い声で狂ったように痛い、苦しいと繰り返す新一を見て快斗は意を決して意識の途切れそうな新一と向き合った。 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 「事情は後でゆっくり聞くわ。それまで逃げずに居てくれるかしら?」 「・・・・・・・ああ」 怒りを露わにして言うと志保は必要なものを取りに阿笠邸へと戻った。 快斗はベッドに横たわる新一を見て安堵のため息を吐いた。あの後、快斗の存在を忘れ苦しみもがく新一からなんとか志保の情報を聞き出し、彼女の迅速な処置によって新一は一命を取りとめた。薬を飲める状態ではなかった新一に注射で薬品を注入すると発作は治まったがぷっつりと意識を飛ばしてしまった。今も点滴から栄養を送り生きている状態で、彼が意識を失ってから丸一日が過ぎようとしていた。 蒼白い顔・・・・・対峙するときはいつもきつく睨まれていたからわからなかったけど、女みたいに綺麗なんだな・・・ こんな風にまじまじと見たことなどなかった。前髪が流れ額が露わになった姿を見るのも初めてだった。形のいい額に手を乗せるとそこはわずかに熱を持っている。 いつも気丈に自分を追い詰める探偵が今は廃人のようにベッドに眠っている。よく見ると腕には点滴や注射針の後がたくさんあって痛々しい。自分のそれより一回り細い腕、首を見ると昨夜の痕が生々しく残っている。首にくっきりと残った痣は数週間は消えないだろう。だがもっと深く傷ついたのは実は快斗のほうであったのかもしれない。 「怪盗さん?もうすぐ工藤君の意識が戻るわ。その前に下で経緯を聞かせてくれないかしら?」 「わかった・・・・・」 リビングには未だ薬が散らばっていた。片付ける気がないのか志保は構わずソファに座る。快斗も向かい側のソファに座り、事の顛末をありのままに話した。 「はぁ・・・・・まったく」 そう呟くと志保は呆れた様子で紅茶を啜り嘆息した。 「怒らないの?」 「怒るも怒らないも、こうなったのは工藤君の責任だもの。意地張って人に頼ろうとしないから、ここまで酷い事になったのよ」 「でもオレ首絞めたんだよ・・・?」 「わたしもそうしたくなる時はあるわ・・・・・」 そう言って伏目がちに紅茶を飲む志保。本気か冗談なのか判断しかねるが、彼女があの探偵を大切に思っていることはすぐにわかった。 ガタガタと上で物音がしたので二人で上に戻る事にした。その時志保に言われた言葉が快斗にはよくわからなかった。 「彼の前で申し訳なさそうな顔をしては駄目よ。謝るのはもっと駄目」 でも・・・と快斗が言いかけた言葉をいいから、と志保は遮った。 キッドは人を殺したりしない。それは親の代からの決まりとなっていた。それをしかけたのだから気に食わない相手でも一言謝ろうと思っていたのに。というより謝るのが普通ではないのか? 疑問を持ちながらも彼女に続いて新一の部屋へ入る。 「具合はどうかしら?」 「頭がいてー」 「ただの微熱よ。それ以外に変わったところは?」 「全身だりー」 「いつもより薬の量が多かったからね・・・今日の分は後で調節して持ってくるわ」 「・・・サンキュー」 「下の薬は後で片しておいて」 「ああ、派手にぶちまけただろ?袋開けたら全部飛び出してきてさ」 「今度から個装にしてあげるわ」 「そうしてもらえると助かる」 後ろで話を聞いていた快斗は病み上がりに薬を片付けさせるのかと志保の非情さに驚き、それを気にする様子もなく会話をする新一に開いた口が塞がらなかった。 「お前まだいたんだ?」 今気付いたかのように快斗を見ると新一が嫌そうに呟いた。 「・・・・・まぁね」 口調がキッドではなくなっているのは当然であった。キッドの衣装のまま家をうろつくのも可笑しいかと普段着でいたのだ。それに今更キッドを演じる気もしなかったので地でいくことにしていた。 「・・・帰れって行ったろ?」 鋭い目つきで凄まれても前のように憎まれ口を返すことができなくなっていた。 「そんなわけにもいかねーだろ・・・・・」 「怪盗さん、家主が帰れって言ってるんだから帰ったら?」 嫌な予感がした志保は早々に二人を引き離そうと快斗を帰そうとするが二人の言い合いは終わらない。 「もしかして悪いことしたとでも思ってるのか?俺は死ななかったんだ、それで義賊のメンツはたっただろ?」 「メンツを気にしてるわけじゃない。お前の身体があんな・・・・・」 「出てけ」 かすれた声だがはっきりとそう言うと新一の眼が殺気立つ。 「なんでだよ・・・オレはただ一言・・」 「ムカつくんだよ・・・さっきから憐れみたっぷりの眼で見やがって・・・」 「そんなつもりは・・・」 確かに前に自分が探偵にとっていた態度とは違う。心の奥では彼のことを可哀想だと思っていることを否定はできない。それが、このプライドの高い探偵には我慢の出来ないことなのだとわかっていても、前のように接することはもうできない。 黙ってしまった快斗から目線を外し、枕に頭を埋めて新一が告げた。 「・・・・・もうどーでもいい。昨日は邪魔すんなって言いに来たんだよな?いいぜ、俺はお前から手を引く。俺に同情してるコソ泥なんかのケツ追っかけてもつまんねーしな。後はせいぜい中森警部と遊んでればいいさ」 「怪盗さん、これ以上ここにいても無駄よ。工藤君の容態が悪化する前に帰ってちょうだい・・・」 二人のやり取りを黙って見ていた志保だが、新一の顔色の変化に気付き、快斗を退席させる。 「・・・・・わかったよ」 後ろ髪を引かれる思いだったが、当初の目的は果たせたのだと自分に言い聞かせその場を去る。 後味の悪さに苛立って玄関でのろのろと靴を履いていると志保が足音も立てずに階段を降りてきた。 「あなたたちは一緒に居ては駄目ね・・・・・近づけば近づくほどお互いの針で相手を傷つけるだけ・・・」 「だったら離れればいいだけだよ」 快斗は金輪際新一とは関わりを持たないつもりで最初で最後となるであろう工藤邸を出て行った。 「それでも近づいてしまうから痛いのでしょう・・・・・・?」 快斗の去った玄関で呟いた志保の言葉は静寂に飲み込まれて霧散した。 to be continue..... あー暗いっ! |